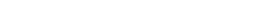Pick Up Contents今月のおすすめ
これからの指導育成を変える「シン・パワハラ研修」
現在、多くの現場では「パワハラの線引きが難しく、指導を躊躇してしまう」という課題が、品質向上や人材定着に影響を及ぼしています 。本研修は、単なる「パワハラ禁止事項の習得」ではありません。アンガーマネジメントによる感情のコントロールや、承認・傾聴・フィードバックという具体的な対人スキルを一体で学び、「正しく導く力」をアップデートします 。人事教育担当者や管理職、OJTリーダーの方々が、自信を持って「育てる関わり方」を実践できる組織づくりを強力にサポートいたします
Facebookビブレンス フェイスブック

ビブレンスチャンネル
株式会社ビブレンスが、これからのビジネスに向けたマナーや知識、アイデア、またそれにまつわるトピックなど、明日から役に立つ良質で有益なコンテンツをお届けして参ります。
チャンネル登録、
いいねボタンをぜひ
よろしくお願い致します!
いいねボタンをぜひ
よろしくお願い致します!
Recommend Bookおすすめ書籍
一生健康に働くための心とカラダの守り方
出版社/かんき出版
<この本との出会い>
今年、私は最愛の母、愛犬、親しい先輩を病気で亡くしました。つい先日まで元気だった身近な存在が、突然いなくなる。周囲からは以前より働き過ぎを心配されていましたが、この経験が、自分の健康と真剣に向き合うきっかけになりました。今が一番脂がのっている時期だからこそ、まだまだこれを続けたい――そう思って手に取ったのが本書です。
<概要>
1万人超のビジネスパーソンと向き合ってきた産業医が、「心と身体の健康」のために留意すべき点を解説。突発性難聴や座りすぎのリスクといった身体の不調から、5人に1人が罹患するというメンタルヘルス不調まで、現代人が直面する健康課題とその対処法を医学的根拠とともに示しています。
<注目ポイント>
・働き方の「限界サイン」を見逃さない
本書で最も印象的だったのは、「昼間に集中できない状態が続く働き方は、3カ月が限度」という指摘です。薬で症状を抑えながら厳しい状況に耐えられるのはせいぜい2〜3カ月。それ以降は体調が一気に崩れる可能性が高いといいます。仕事に集中できない症状が出た時、その終わりが見えていなければ、せめて上司に相談し、業務をセーブするなど体調改善を優先させる必要があるのです。
・「笑顔」と「挨拶」という処方箋
メンタルヘルス不調への対処法として、著者が強調するのが「笑う機会を意図的に作ること」と「どんな時も挨拶だけはすること」。好きな動画や笑える写真を見て笑顔になると、脳内でエンドルフィンが分泌されストレスが和らぎます。また、挨拶は気を遣わずに発することができ、周囲とのつながりを維持する最適なコミュニケーションツールになるといいます。
研修の現場でも、参加者からメンタル不調時のコンディションの整え方をよく聞かれます。睡眠やリフレッシュの重要性は伝えていましたが、今後は「笑い」や「挨拶」の効用も積極的に伝えていきたいと思いました。
・身体からの「防御反応」を理解する
忙しい時に疲れやすくなるのは、身体が「これ以上動くと危険」と判断し、休むべきだとシグナルを送っているためです。この「身体の防御反応」を無視せず、十分な休養と睡眠を確保すること。また、自分に出やすい症状(頭痛、不眠、腹痛など)を覚えておき、その症状が出たら「1日休む」といった対策を立てておくことの重要性が説かれています。
<実践への示唆>
本書が教えてくれるのは、健康管理は「深刻な状態になる前の日常的な習慣」だということです。座りすぎない工夫、肌の状態をバロメーターにする、笑う機会を作る、体調不良のサインを見逃さない――これらは特別なことではなく、毎日の仕事の中で実践できることばかりです。
人材育成に携わる立場から見ても、メンバーの健康管理は組織の持続可能性に直結します。「頑張りすぎ」を美徳とせず、適切なタイミングで休むことの重要性を、リーダー自身が体現し、チームに浸透させていく必要があると痛感しました。
<こんな人におすすめ>
なかなか疲れ(肉体的にも心理的にも)が取れないと感じているビジネスパーソンに強くお勧めします。「まだ大丈夫」と思っている今こそ読むべき一冊です。深刻な状態になる可能性は誰にでもあります。自分の健康を守ることは、大切な人や仕事を守ることにもつながります。427ページ、1,980円という内容の濃さと実用性を考えれば、投資する価値は十分にあります。
今年、私は最愛の母、愛犬、親しい先輩を病気で亡くしました。つい先日まで元気だった身近な存在が、突然いなくなる。周囲からは以前より働き過ぎを心配されていましたが、この経験が、自分の健康と真剣に向き合うきっかけになりました。今が一番脂がのっている時期だからこそ、まだまだこれを続けたい――そう思って手に取ったのが本書です。
<概要>
1万人超のビジネスパーソンと向き合ってきた産業医が、「心と身体の健康」のために留意すべき点を解説。突発性難聴や座りすぎのリスクといった身体の不調から、5人に1人が罹患するというメンタルヘルス不調まで、現代人が直面する健康課題とその対処法を医学的根拠とともに示しています。
<注目ポイント>
・働き方の「限界サイン」を見逃さない
本書で最も印象的だったのは、「昼間に集中できない状態が続く働き方は、3カ月が限度」という指摘です。薬で症状を抑えながら厳しい状況に耐えられるのはせいぜい2〜3カ月。それ以降は体調が一気に崩れる可能性が高いといいます。仕事に集中できない症状が出た時、その終わりが見えていなければ、せめて上司に相談し、業務をセーブするなど体調改善を優先させる必要があるのです。
・「笑顔」と「挨拶」という処方箋
メンタルヘルス不調への対処法として、著者が強調するのが「笑う機会を意図的に作ること」と「どんな時も挨拶だけはすること」。好きな動画や笑える写真を見て笑顔になると、脳内でエンドルフィンが分泌されストレスが和らぎます。また、挨拶は気を遣わずに発することができ、周囲とのつながりを維持する最適なコミュニケーションツールになるといいます。
研修の現場でも、参加者からメンタル不調時のコンディションの整え方をよく聞かれます。睡眠やリフレッシュの重要性は伝えていましたが、今後は「笑い」や「挨拶」の効用も積極的に伝えていきたいと思いました。
・身体からの「防御反応」を理解する
忙しい時に疲れやすくなるのは、身体が「これ以上動くと危険」と判断し、休むべきだとシグナルを送っているためです。この「身体の防御反応」を無視せず、十分な休養と睡眠を確保すること。また、自分に出やすい症状(頭痛、不眠、腹痛など)を覚えておき、その症状が出たら「1日休む」といった対策を立てておくことの重要性が説かれています。
<実践への示唆>
本書が教えてくれるのは、健康管理は「深刻な状態になる前の日常的な習慣」だということです。座りすぎない工夫、肌の状態をバロメーターにする、笑う機会を作る、体調不良のサインを見逃さない――これらは特別なことではなく、毎日の仕事の中で実践できることばかりです。
人材育成に携わる立場から見ても、メンバーの健康管理は組織の持続可能性に直結します。「頑張りすぎ」を美徳とせず、適切なタイミングで休むことの重要性を、リーダー自身が体現し、チームに浸透させていく必要があると痛感しました。
<こんな人におすすめ>
なかなか疲れ(肉体的にも心理的にも)が取れないと感じているビジネスパーソンに強くお勧めします。「まだ大丈夫」と思っている今こそ読むべき一冊です。深刻な状態になる可能性は誰にでもあります。自分の健康を守ることは、大切な人や仕事を守ることにもつながります。427ページ、1,980円という内容の濃さと実用性を考えれば、投資する価値は十分にあります。
もっと見る
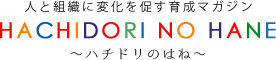
「ハチドリのはね」へ(外部サイト)
ウェブマガジン「ハチドリのはね」にてコラム連載中!
ウェブマガジン「ハチドリのはね」にて毎週木曜日更新でコラムを連載しております。 「これからのオンラインとの向き合い方」と題して、オンラインツールを柱にした社内教育や情報共有のポイントをお伝えしています。ぜひご覧ください。

私たちビブレンスは、 目標、 勇気、 行動の3つをベースに
「わくわくするような職場、 人材 、仕事」
の価値創造をお手伝いします。

ビブレンスは、『4つのソリューション』をご提案致します。

ビブレンスについて


業務実績


パートナーコンサルタント


業務の流れ


お問い合わせ

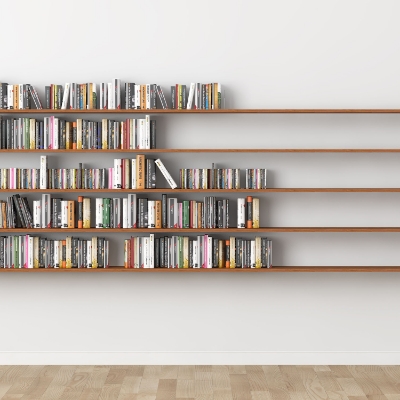
おすすめ書籍