ビブレンス代表、益田が自信を持っておすすめする、仕事に、人生に、人間関係にとても役に立つ本たちをご紹介致します。
「有益な本を読みたいけれど何を読めばいいのかわからない!」
そんなあなたの参考の一助になれば幸いです。
本のカバーをクリック・タップすると益田の解説文が表示されます。
ぜひごゆっくり御覧ください。
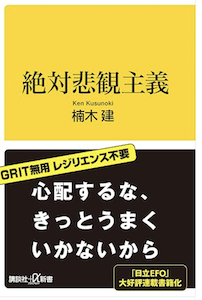
✕
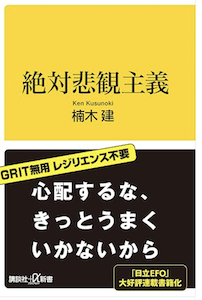
絶対悲観主義
出版社/講談社
<所感>
コロナ禍のとき、出口戦略というかアフターコロナのビジョンがイメージしづらいなぁという足踏み状態の中で、タイトルをみて即買いした一冊。サブタイトルの「心配するな、きっとうまくいかないから」はインパクトがあります。皮肉なことに当時、GRID(やり抜く力)やレジリエンス(折れない心)の研修を設計していたので、なおさら興味を惹かれました。「どうせうまくいかない」としながら、あきらめるわけではなく、過度な期待や成功への執着から自身をを解放することで、気持ちよく取り組めるようになる行動哲学です。
<学びのポイント>
・事前期待が低いとプレッシャーもなく、気軽に速やかに取りかかれる
・失敗やリスクへの耐性が強くなる
・良い意味で自分の都合に固執しなくなる
・最大の不幸は他人への嫉妬である
・生活の充実は「今・ここ」にしかない
・ブランディングよりもブランデッド
・アウトサイドインよりインサイドアウト
・品の良さの最上の定義は「欲望に対する速度が遅い」
・失敗したときに大事なのは「待つ力」
・名言の三条件「本質的」「実用的」「短い」
<まとめ>
何事にも「頑張る」ことは大事なのですが、(意識・無意識関係なく)過度に頑張りすぎようとして、自分を追い込んだり、萎縮して能力を発揮できなかったりするのは、考え直さないといけないですね。うまくいったらもうけもの、やるだけのことはやってみよう、ダメならまた次があるじゃないかぐらいがいいんだと思いました。これこそが、今の時代におけるメンタルケアに必要な考え方ではないかと思いました。
コロナ禍のとき、出口戦略というかアフターコロナのビジョンがイメージしづらいなぁという足踏み状態の中で、タイトルをみて即買いした一冊。サブタイトルの「心配するな、きっとうまくいかないから」はインパクトがあります。皮肉なことに当時、GRID(やり抜く力)やレジリエンス(折れない心)の研修を設計していたので、なおさら興味を惹かれました。「どうせうまくいかない」としながら、あきらめるわけではなく、過度な期待や成功への執着から自身をを解放することで、気持ちよく取り組めるようになる行動哲学です。
<学びのポイント>
・事前期待が低いとプレッシャーもなく、気軽に速やかに取りかかれる
・失敗やリスクへの耐性が強くなる
・良い意味で自分の都合に固執しなくなる
・最大の不幸は他人への嫉妬である
・生活の充実は「今・ここ」にしかない
・ブランディングよりもブランデッド
・アウトサイドインよりインサイドアウト
・品の良さの最上の定義は「欲望に対する速度が遅い」
・失敗したときに大事なのは「待つ力」
・名言の三条件「本質的」「実用的」「短い」
<まとめ>
何事にも「頑張る」ことは大事なのですが、(意識・無意識関係なく)過度に頑張りすぎようとして、自分を追い込んだり、萎縮して能力を発揮できなかったりするのは、考え直さないといけないですね。うまくいったらもうけもの、やるだけのことはやってみよう、ダメならまた次があるじゃないかぐらいがいいんだと思いました。これこそが、今の時代におけるメンタルケアに必要な考え方ではないかと思いました。

✕
若者に辞められると困るので、強く言えません
出版社/東洋経済新報社
昨今、部下に”ワカモノ”が抱えているほとんどの方が、このような気持ちを持っているのではないでしょうか。表紙に記載された「ゆるくてもダメ、ブラックはもちろんダメ、どう関わるのが正解?」という問いに対して、サブタイトルの「マネジャーの心の負担を減らす11のルール」という角度で、わかりやすく整理してあります。
<学びのポイント>
・部下の問題行動を変える3種類の働きかけ「叱る」「注意する」「指摘する」を場面に応じて適切に使い分ける
・主体性を強化するために「目的」を繰り返し言葉にさせる
・スピードと完成度ならスピードを優先すべき。そのほうが結果として成長につながる
・「反省の気づき」より「発見の気づき」を増やす
・「向き不向き」ではなく「慣れ不慣れ」である
・大事なことは失敗した後にどのようにフォローするか
・「責任」「権限」「義務」の三角関係をよく理解させる
・「強み」を伸ばすためにも部下に関心をもつ
・「共創」よりも「競争」チームには適度な緊張感が必要
・「やりたい仕事」と「やりがいのある仕事」は全然違う
・正確に伝えるなら「オンライン一択」ただし人間関係がないうちは「リアル」で
筆者が冒頭で「重要なことは時代や環境に応じた適切な『バランス』を見つけることだ。」と書いてありますが、そのバランスについて11の比較視点を示してくれており、具体的な場面も想定しやすいです。昨今は「心理的安全性」が叫ばれる中、どうしてもソフト路線な指導に偏ってしまう傾向になりがちです。主体的・継続的に部下が成長できるような環境をつくるためにも、自職場における最適解を模索し続けることが大事であると再認識しました。
<学びのポイント>
・部下の問題行動を変える3種類の働きかけ「叱る」「注意する」「指摘する」を場面に応じて適切に使い分ける
・主体性を強化するために「目的」を繰り返し言葉にさせる
・スピードと完成度ならスピードを優先すべき。そのほうが結果として成長につながる
・「反省の気づき」より「発見の気づき」を増やす
・「向き不向き」ではなく「慣れ不慣れ」である
・大事なことは失敗した後にどのようにフォローするか
・「責任」「権限」「義務」の三角関係をよく理解させる
・「強み」を伸ばすためにも部下に関心をもつ
・「共創」よりも「競争」チームには適度な緊張感が必要
・「やりたい仕事」と「やりがいのある仕事」は全然違う
・正確に伝えるなら「オンライン一択」ただし人間関係がないうちは「リアル」で
筆者が冒頭で「重要なことは時代や環境に応じた適切な『バランス』を見つけることだ。」と書いてありますが、そのバランスについて11の比較視点を示してくれており、具体的な場面も想定しやすいです。昨今は「心理的安全性」が叫ばれる中、どうしてもソフト路線な指導に偏ってしまう傾向になりがちです。主体的・継続的に部下が成長できるような環境をつくるためにも、自職場における最適解を模索し続けることが大事であると再認識しました。

✕
最後は言い方―これだけでチームが活きる究極のスキル
出版社/東洋経済新報社
お友達の橋口君が薦めてくれた本。昨年のうちにざっと読んでいたのですが、レビュー書いてなかったので、研修で活用することも考えて整理してみました。基本的には組織の心理的安全性をどのように担保していくのか、そのヒントが書かれています。
<学びのポイント>
リーダー自身がマネジメントにおける前提というか価値観を見直す必要があります。それが6つのポイントで整理されています。
①時計を支配する(間違いそうだと思ったらすぐに中断できるようにする)
②メンバーと連携する(誰もが意見をいいやすい環境、異論を積極的に受け容れる)
③責任感を自覚して取り組む(自分の考えを押しつけるのではなく、自分事として捉えさせるようにする)
④事前に定めた目標を達成したら区切りをつける(勢いのまま続行させない)
⑤成果を改善する(ミスを問うのではなく、良い方向に伸びるように問いかける)
⑥垣根を越えて繋がる(全方位的に関係者に目をやり、気にかける、胸襟を開く)
それぞれにおいて具体的ば場面を引用した、適切な「物言い」を解説しています。
また考える仕事は「青ワーク」、実行するのは「赤ワーク」として、それぞれの進め方の違いも解説した上で、
使う(投げかける)言葉を選ぶようにしています。バランスも必要です。
個人的には、心理的安全性のある組織づくりについて、視野が広がったような気がします。
やはり大前提となる考え方を変えていかないと、先に進みませんね。
情報量が多いので、読み込むのに時間はかかりますが
その分、すぐに使えそうな内容も満載ですので、オススメします。
<学びのポイント>
リーダー自身がマネジメントにおける前提というか価値観を見直す必要があります。それが6つのポイントで整理されています。
①時計を支配する(間違いそうだと思ったらすぐに中断できるようにする)
②メンバーと連携する(誰もが意見をいいやすい環境、異論を積極的に受け容れる)
③責任感を自覚して取り組む(自分の考えを押しつけるのではなく、自分事として捉えさせるようにする)
④事前に定めた目標を達成したら区切りをつける(勢いのまま続行させない)
⑤成果を改善する(ミスを問うのではなく、良い方向に伸びるように問いかける)
⑥垣根を越えて繋がる(全方位的に関係者に目をやり、気にかける、胸襟を開く)
それぞれにおいて具体的ば場面を引用した、適切な「物言い」を解説しています。
また考える仕事は「青ワーク」、実行するのは「赤ワーク」として、それぞれの進め方の違いも解説した上で、
使う(投げかける)言葉を選ぶようにしています。バランスも必要です。
個人的には、心理的安全性のある組織づくりについて、視野が広がったような気がします。
やはり大前提となる考え方を変えていかないと、先に進みませんね。
情報量が多いので、読み込むのに時間はかかりますが
その分、すぐに使えそうな内容も満載ですので、オススメします。

✕
「指示通り」ができない人たち
出版社/日経プレミアシリーズ
昨今の職場を悩ます”使えないなぁ。。。。”といった方々について心理学者である著者が考察した本です。指示通りのことがこなせない、メンタルが弱くすぐ心が折れる、自己評価がやたら高い…といった、アンビリーバルな行動に対して、管理職はどのように対応していけばいいのかを様々な事例ともに紹介しています。
<学びのポイント>
●職場で使えない人材の問題点は以下の3つ。
①認知能力の問題
知的能力である認知能力、中でも読解力が弱く、書いてあることや人の話を十分に理解できない。
②メタ認知能力の問題
「振り返る力」が弱く、自分の仕事能力の弱点に気づけないため、改善・成長ができない。
③非認知能力の問題
自分をやる気にさせる力などの非認知能力に問題があり、知的活動がうまくいかない。
●認知能力・メタ認知能力・非認知能力が低い人の特徴と、管理職がすべき対処法とは、例えば、次のようなものである。
【認知能力が低い人】
・何かとすぐにパニックになってしまう。
⇒同時に複数のことをしないようにさせる。
・頭の中が整理されておらず、指示通りに動けない。
⇒文章を要約するなど、要点を抽出する訓練を行わせる。
【メタ認知能力が低い人】
・先輩からのアドバイスを意地悪と受け止める。
⇒対話を重ねて、自分のやり方が間違っていたことに気づいてもらい、アドバイスを冷静に受け止めるよう導く。
・仕事ができないのに、できるつもりでいる。
⇒仕事の注意点等について自問自答する習慣をつけさせる。
【非認知能力が低い人】
・思うような成果が出ないと落ち込む。
⇒失敗を前向きに受け止める習慣をつけさせ、レジリエンス(回復力)を高める。
・仕事の能力は高いが、人と接するのが苦手。
⇒仕事に関する知識が豊富なことに自信を持つよう伝える
読み終わっての正直な感想は「現場はここまで深刻なのか」ということ。研修でも様々相談されますが、発達障害という言葉で大きく括って、本質的な解決に踏み込めていないのが実情です。かなり深刻な問題ですが、これは学校教育も絡めて改善していかないと、会社の上司、人事、研修部門だけでは対応できないような気がします。これもスマホ依存の影響なのか。本気で取り組まないと。特に採用で苦戦している中小企業にとっては、一層深刻な問題であると推察します。
<学びのポイント>
●職場で使えない人材の問題点は以下の3つ。
①認知能力の問題
知的能力である認知能力、中でも読解力が弱く、書いてあることや人の話を十分に理解できない。
②メタ認知能力の問題
「振り返る力」が弱く、自分の仕事能力の弱点に気づけないため、改善・成長ができない。
③非認知能力の問題
自分をやる気にさせる力などの非認知能力に問題があり、知的活動がうまくいかない。
●認知能力・メタ認知能力・非認知能力が低い人の特徴と、管理職がすべき対処法とは、例えば、次のようなものである。
【認知能力が低い人】
・何かとすぐにパニックになってしまう。
⇒同時に複数のことをしないようにさせる。
・頭の中が整理されておらず、指示通りに動けない。
⇒文章を要約するなど、要点を抽出する訓練を行わせる。
【メタ認知能力が低い人】
・先輩からのアドバイスを意地悪と受け止める。
⇒対話を重ねて、自分のやり方が間違っていたことに気づいてもらい、アドバイスを冷静に受け止めるよう導く。
・仕事ができないのに、できるつもりでいる。
⇒仕事の注意点等について自問自答する習慣をつけさせる。
【非認知能力が低い人】
・思うような成果が出ないと落ち込む。
⇒失敗を前向きに受け止める習慣をつけさせ、レジリエンス(回復力)を高める。
・仕事の能力は高いが、人と接するのが苦手。
⇒仕事に関する知識が豊富なことに自信を持つよう伝える
読み終わっての正直な感想は「現場はここまで深刻なのか」ということ。研修でも様々相談されますが、発達障害という言葉で大きく括って、本質的な解決に踏み込めていないのが実情です。かなり深刻な問題ですが、これは学校教育も絡めて改善していかないと、会社の上司、人事、研修部門だけでは対応できないような気がします。これもスマホ依存の影響なのか。本気で取り組まないと。特に採用で苦戦している中小企業にとっては、一層深刻な問題であると推察します。

✕
やる気に頼らず「すぐやる人」になる37のコツ
出版社/Kindle版
段取りに関する研修をやっていますが、仕事のスピードをアップするためには「着手する力、始める力」は重要なポイントです。
講義内容やコンテンツの伝え方を再確認する上での、参考資料として手に取ってみました。
<学びのポイント>
・あれこれ考えるより、仮決めして仮行動を起こす
・行動着手の着火剤として、まず10秒動いてみる
・朝一でやることを決めておく。朝のスタートがいいと1日はうまくいく
・1日の時間割を決める。5つの時間帯。「就業前」「午前中」「15時まで」「勤務終了まで」「就寝まで」
・本気で集中する時間を30分、1日2回設定する
・既に習慣になっていることに、これから習慣にしたいことをくっつけてみる
個人的には、「やる気に頼らない」という考え方に興味があります。
最終的にはやる気というか気持ち次第なのですが
これを補うだけのしくみやしかけをどれだけ設定できるかがポイントだと思いました。
あとは少しずつ行動を増やしていくことと、うまくいかなくても気にせずまたやり直すこと。
自分の力量も踏まえて、無理をしないことも大事だと思います。
講義内容やコンテンツの伝え方を再確認する上での、参考資料として手に取ってみました。
<学びのポイント>
・あれこれ考えるより、仮決めして仮行動を起こす
・行動着手の着火剤として、まず10秒動いてみる
・朝一でやることを決めておく。朝のスタートがいいと1日はうまくいく
・1日の時間割を決める。5つの時間帯。「就業前」「午前中」「15時まで」「勤務終了まで」「就寝まで」
・本気で集中する時間を30分、1日2回設定する
・既に習慣になっていることに、これから習慣にしたいことをくっつけてみる
個人的には、「やる気に頼らない」という考え方に興味があります。
最終的にはやる気というか気持ち次第なのですが
これを補うだけのしくみやしかけをどれだけ設定できるかがポイントだと思いました。
あとは少しずつ行動を増やしていくことと、うまくいかなくても気にせずまたやり直すこと。
自分の力量も踏まえて、無理をしないことも大事だと思います。

✕
科学的根拠に基づく最高の勉強法
出版社/KADOKAWA
YouTubeで300万回再生されている大人気の動画「科学的根拠に基づく最高の勉強法」が詳細版として書籍リリースされました。
とにかく衝撃だったのは、冒頭から今まで当たり前にようにやってきた「何度も読む、ノートに書く、蛍光ペンやアンダーラインを引く」というのは、あまり効果的な学習方法でないことが、科学的に証明されています。
<学びのポイント>
・これまでの学習法「再読、ノートへの書写やまとめ、重要ポイントの線引き」は思ったより効果が薄い
・決定的に重要なのが「アクティブリコール(勉強したことや覚えたいことを、能動的に思い出すこと、記憶から引き出すこと)」
・一度にまとめて勉強するよりも、時間を分散して勉強するほうが長期的な記憶の定着がいい。
・何故なのかという問いと勉強している内容の説明はできるようにしておくと定着がいい
個人的には、勉強した気になっている自分というのが気になりました。インプットも大事ですが、どれだけアウトプットできるはもっと重要です。
とにかく衝撃だったのは、冒頭から今まで当たり前にようにやってきた「何度も読む、ノートに書く、蛍光ペンやアンダーラインを引く」というのは、あまり効果的な学習方法でないことが、科学的に証明されています。
<学びのポイント>
・これまでの学習法「再読、ノートへの書写やまとめ、重要ポイントの線引き」は思ったより効果が薄い
・決定的に重要なのが「アクティブリコール(勉強したことや覚えたいことを、能動的に思い出すこと、記憶から引き出すこと)」
・一度にまとめて勉強するよりも、時間を分散して勉強するほうが長期的な記憶の定着がいい。
・何故なのかという問いと勉強している内容の説明はできるようにしておくと定着がいい
個人的には、勉強した気になっている自分というのが気になりました。インプットも大事ですが、どれだけアウトプットできるはもっと重要です。

✕
ロジカルダイエット
出版社/幻冬舎
この手の本は何冊も読んできましたが、タイトルに惹かれて買いました(笑)タイトルの通り、わかってはいるけど、なるほどそうだよねということが、体系的に書かれていました。
<学びのポイント>
・ラクして痩せる方法はない。そして無理もだめ。
・痩せるということを「体脂肪を落とす」という前提にする
・運動では痩せられないと割り切る。食事で痩せる
・とはいえ、有酸素運動や筋トレはダイエットの土台づくりになる
・食べていいカロリー摂取量は34×自分の体重
・楽なダイエットはない、長い時間をかけてじっくりやる
個人的には、巻末記載の「やせている人の生活習慣12条」の中にあった「おなかいっぱいになったら食べるのをやめる」が心に刺さりました。飲んだ後のラーメンとかは絶対やめないといけないですね。。。。
<学びのポイント>
・ラクして痩せる方法はない。そして無理もだめ。
・痩せるということを「体脂肪を落とす」という前提にする
・運動では痩せられないと割り切る。食事で痩せる
・とはいえ、有酸素運動や筋トレはダイエットの土台づくりになる
・食べていいカロリー摂取量は34×自分の体重
・楽なダイエットはない、長い時間をかけてじっくりやる
個人的には、巻末記載の「やせている人の生活習慣12条」の中にあった「おなかいっぱいになったら食べるのをやめる」が心に刺さりました。飲んだ後のラーメンとかは絶対やめないといけないですね。。。。

✕
スティーブ・ジョブズ 驚異のイノベーション
出版社/日経BP社
没後12年経過しても、その天才的な技術力やマーケティングセンスが語り継がれるスティーブジョブズ。DX化推進の業務依頼が増えてくる過程で、DXの本来の目的や切り拓いていく未来像について、自分自身から再度覚醒しようと思い、改めて読み直しました。イノベーターやクリエーターとしてどうあるべきか、刺激を与えてくれる一冊です。
<学びのポイント>
ジョブズは、次の「7つの法則」に基づいて行動することで、イノベーションを成功させている。
1.大好きなことをする→とりつかれるほど夢中になる
2.宇宙に衝撃を与える→ビジョンで周りを巻き込む
3.頭に活を入れる→様々な分野の疑問や課題や考えを上手につなぎ合わせる力
4.製品を売るな、夢を売れ→顧客のほしいものを一生懸命考える
5.1000ものことにノーと言う→良いものも捨てることで大事なことに絞り込める
6.めちゃくちゃすごい体験を作る→斬新なアイデアをどんどん生み出す
7.メッセージの名人になる→効果的な伝え方を意識する
個人的には「イノベーションは取り憑かれたと思うほど情熱を傾ける人がいなければ生まれない」というくだりが印象に残りました。一定の成功を収めている人は、取り憑かれたような情熱を注いでいることは、これまでいくつも紹介されてきました。自分自身も改めて取り憑かれるような情熱を注いで仕事に取り組みたいと思いました。
<学びのポイント>
ジョブズは、次の「7つの法則」に基づいて行動することで、イノベーションを成功させている。
1.大好きなことをする→とりつかれるほど夢中になる
2.宇宙に衝撃を与える→ビジョンで周りを巻き込む
3.頭に活を入れる→様々な分野の疑問や課題や考えを上手につなぎ合わせる力
4.製品を売るな、夢を売れ→顧客のほしいものを一生懸命考える
5.1000ものことにノーと言う→良いものも捨てることで大事なことに絞り込める
6.めちゃくちゃすごい体験を作る→斬新なアイデアをどんどん生み出す
7.メッセージの名人になる→効果的な伝え方を意識する
個人的には「イノベーションは取り憑かれたと思うほど情熱を傾ける人がいなければ生まれない」というくだりが印象に残りました。一定の成功を収めている人は、取り憑かれたような情熱を注いでいることは、これまでいくつも紹介されてきました。自分自身も改めて取り憑かれるような情熱を注いで仕事に取り組みたいと思いました。

✕
1位思考
出版社/ダイアモンド社
ガジェット好きで出張の多い私は、バッテリーや充電器でコスパのいいものを常に買い求めてきましたが、そのお気に入りなのが「アンカー・ジャパン」創業9年目で売上300億円、オンライン市場ではシェア1位を獲得しています。後発ながらも競争を勝ち抜く極意はどこにあるのか。躍進の背景にある習慣と思考、CEO自らが語った一冊です。
<学びのポイント>
・事業継続のために「負けないゲーム」をする。コア事業で利益を上げつつ新事業を立ち上げる。
・レッドオーシャンの中で、差別化できる強みを見つける。また、それを常にお客様目線で磨き続ける。
・製品は「永遠のベータ版」と捉え、開発・発売後も常にアップデートを継続し、バリューを生み出す
・お客さまと直接コミュニケーションを取り、意見を聞き、製品に反映する。
・意思決定をすばやく行う。経営者が下す意思決定の数が、メンバーの成果、成長につながる。
・ちょっとしたことにこだわり続け、100%を目指す。それがやりきれたときに、圧倒的な強みになる。
・1%にこだわる習慣を組織全体に定着させる。そうすることで、皆で高め合い、前向きに成長していく集団になる。
個人的には、「永遠のベータ版をアップデートし続ける」「お客さまの声を聞く」「小さなこと(1%)にこだわる」等、シンプルなことばかりですが、継続してやり続けることが案外難しいことを大事にしているんだなと感じました。
<学びのポイント>
・事業継続のために「負けないゲーム」をする。コア事業で利益を上げつつ新事業を立ち上げる。
・レッドオーシャンの中で、差別化できる強みを見つける。また、それを常にお客様目線で磨き続ける。
・製品は「永遠のベータ版」と捉え、開発・発売後も常にアップデートを継続し、バリューを生み出す
・お客さまと直接コミュニケーションを取り、意見を聞き、製品に反映する。
・意思決定をすばやく行う。経営者が下す意思決定の数が、メンバーの成果、成長につながる。
・ちょっとしたことにこだわり続け、100%を目指す。それがやりきれたときに、圧倒的な強みになる。
・1%にこだわる習慣を組織全体に定着させる。そうすることで、皆で高め合い、前向きに成長していく集団になる。
個人的には、「永遠のベータ版をアップデートし続ける」「お客さまの声を聞く」「小さなこと(1%)にこだわる」等、シンプルなことばかりですが、継続してやり続けることが案外難しいことを大事にしているんだなと感じました。

✕
ハーバード流マネジメント講座 90日で成果を出すリーダー
出版社/翔泳社
主要顧客某社で人事異動がありました。旧知の方より異動のご挨拶メールを頂戴しまして、新天地での職場変革や成果創出への意気込みを感じました。昔からよく「異動してから最初の3ヶ月(90日)が勝負」とよく言われます。この期間をどう乗り切るかで今後が決まるということですが、では3ヶ月(90日)の間にやるべきことはどういったことなのか? リーダーのキャリア移行を支援する著者が、新任管理職がおさえておくべきガイドラインをレクチャーしています。
<学びのポイント>
・組織運営において必要な知識を、誰から(どこで)どのように学べばよいかを把握する
・自分の置かれた状況を把握しそれに合った戦略を立てる。
・新しい上司と積極的、継続的に会話して信頼関係を築く。
・短期的に成果がでるような案件をつくり、メンバーと協働で取り組む
・組織構造の4つの要素(戦略的方向性、構造、コアプロセス、スキルベース)を分析する。
・メンバーの強みを引き出し、それに合った仕事を与える
・ビジョン達成に向けてのキーマンを見極め、巻き込むためのシナリオを立てる
・自己管理に日々取り組む。
個人的に大事だと感じたのは「新しい上司との関係構築」です。新天地では、慣れないことやわからないことも多く最初は”手探り状態”が続くと思います。そんな状況で、どこで勝負をかければいいか、メンバーにどんな働きかけをすればいいか、それを俯瞰的に判断できるのはやはり上司です。マメな「報・連・相」で信頼関係を築き、自分の見方(後ろ盾)にすることは必須かと思います。またマメな報・連・相によって、上司の方針や判断基準も早期に理解できるので、チーム方針や優先順位へのズレも少なくなり、結果としてとるべきアクションにムダが少なくなると思います。上司をいかにして取り込むか、スタートダッシュで時間をかけたいところです。
<学びのポイント>
・組織運営において必要な知識を、誰から(どこで)どのように学べばよいかを把握する
・自分の置かれた状況を把握しそれに合った戦略を立てる。
・新しい上司と積極的、継続的に会話して信頼関係を築く。
・短期的に成果がでるような案件をつくり、メンバーと協働で取り組む
・組織構造の4つの要素(戦略的方向性、構造、コアプロセス、スキルベース)を分析する。
・メンバーの強みを引き出し、それに合った仕事を与える
・ビジョン達成に向けてのキーマンを見極め、巻き込むためのシナリオを立てる
・自己管理に日々取り組む。
個人的に大事だと感じたのは「新しい上司との関係構築」です。新天地では、慣れないことやわからないことも多く最初は”手探り状態”が続くと思います。そんな状況で、どこで勝負をかければいいか、メンバーにどんな働きかけをすればいいか、それを俯瞰的に判断できるのはやはり上司です。マメな「報・連・相」で信頼関係を築き、自分の見方(後ろ盾)にすることは必須かと思います。またマメな報・連・相によって、上司の方針や判断基準も早期に理解できるので、チーム方針や優先順位へのズレも少なくなり、結果としてとるべきアクションにムダが少なくなると思います。上司をいかにして取り込むか、スタートダッシュで時間をかけたいところです。

✕
学習する組織 システム思考で未来を創造する
出版社/英治出版
環境変化の激しい昨今、組織としてどのように適応し、学習・進化し続けていく「学習能力」についての考え方と手法を解説した1冊です。
<学びのポイント>
経営に失敗した企業は、事前に苦境に陥っている状況が見られるが、たいていそれは見過ごされる。それは組織が「学習障害」に陥っているからである。そうならないためにも「学習する組織」を創らなければならない。
●「学習する組織」を築く上で必要な要素は、次の5つである。
①システム思考
「システム思考」は、相互関係、全体を見るための枠組みである。複雑な状況の根底にある構造を見る上で欠かせない。
②自己マスタリー
「自己マスタリー」は、個人の成長と学習のための理論と手法を意味する。学習する組織の精神は 、高度な自己マスタリーに達した人たちの、たゆまぬ学びの探求から生まれる。
③メンタル・モデル
「メンタル・モデル」とは、世の中とはこういうものだという心に染みついたイメージのこと。新しい見識を実行に移せないのは、その見識が、世の中とはこういうものだという心に染みついたイメージと対立するから。学習する組織を築く際は、これを検証し、改善することが大切である。
④共有ビジョン
「共有ビジョン」とは、組織中のあらゆる人々が思い描くイメージのこと。これがあることによって、学習の焦点が絞られ、そして学習のエネルギーが生まれる。
⑤チーム学習
「チーム学習」は、メンバーが望む結果を出せるよう、チームの能力を揃え、伸ばすプロセスである。「ダイアログ」と「ディスカッション」を習得する必要がある。
個人的に感じたのは「メンタルモデル」に影響されている組織が多いということ。自分たちの了見だけで捉えると、思考停止が続いてしまう。新たなことに取り組む前に、自分たちのものの捉え方、考え方をきちんと分析しないといけないと痛感しました。
<学びのポイント>
経営に失敗した企業は、事前に苦境に陥っている状況が見られるが、たいていそれは見過ごされる。それは組織が「学習障害」に陥っているからである。そうならないためにも「学習する組織」を創らなければならない。
●「学習する組織」を築く上で必要な要素は、次の5つである。
①システム思考
「システム思考」は、相互関係、全体を見るための枠組みである。複雑な状況の根底にある構造を見る上で欠かせない。
②自己マスタリー
「自己マスタリー」は、個人の成長と学習のための理論と手法を意味する。学習する組織の精神は 、高度な自己マスタリーに達した人たちの、たゆまぬ学びの探求から生まれる。
③メンタル・モデル
「メンタル・モデル」とは、世の中とはこういうものだという心に染みついたイメージのこと。新しい見識を実行に移せないのは、その見識が、世の中とはこういうものだという心に染みついたイメージと対立するから。学習する組織を築く際は、これを検証し、改善することが大切である。
④共有ビジョン
「共有ビジョン」とは、組織中のあらゆる人々が思い描くイメージのこと。これがあることによって、学習の焦点が絞られ、そして学習のエネルギーが生まれる。
⑤チーム学習
「チーム学習」は、メンバーが望む結果を出せるよう、チームの能力を揃え、伸ばすプロセスである。「ダイアログ」と「ディスカッション」を習得する必要がある。
個人的に感じたのは「メンタルモデル」に影響されている組織が多いということ。自分たちの了見だけで捉えると、思考停止が続いてしまう。新たなことに取り組む前に、自分たちのものの捉え方、考え方をきちんと分析しないといけないと痛感しました。

✕
イノベーションの競争戦略 優れたイノベーターは0→1か? 横取りか?
出版社/東洋経済新報社
近年日本企業から「イノベーション」が生まれない理由を「イノベーションの本質」がわかっていないとういう角度から分析。技術革新=イノベーションではない。「顧客の暮らしを変えること」こそが本質として、そこに向けた行動変容のメカニズムを解説した一冊です。
<学びのポイント>
●イノベーションとは、これまでにない価値の創造により、顧客の行動が変わることである。
●イノベーションを引き起こす源泉は、次の3つである。
・社会構造 ・心理変化 ・技術革新
これらを「イノベーションのドライバー(トライアングルドライバー)」と呼ぶ
●イノベーションは、①トライアングルでドライバーを捉える、②ドライバーをてこに新しい価値を創造する、③顧客の態度が変容する、④顧客の行動が変容する、という4ステップで起こる。この創出プロセスを「イノベーションストリーム」と呼ぶ。
●行動変容を起こす者と、価値創造を実現する者が、同じとは限らない。新しい価値を創造しても、顧客の行動をどう変えるのかという広い視野がないと、イノベーターにはなれない。逆に言うと、新しい価値を創造できなくても、顧客の行動変容と実現したいことを明確にすれば、イノベーターになれる。
●イノベーションの達成後、その行動変容をベースに新たなイノベーションを生み出すことができる。この「イノベーションの連続」で重要なのは、「行動変容」→ 新たな「ドライバー」を見立てる →「価値創造」とプロセスを進めていくことだ。
個人的には、イノベーション達成後に新しいイノベーションを生み出す「連続的イノベーション」は日本企業の伝統的な強みですので、意識すべき点だと思いました。
<学びのポイント>
●イノベーションとは、これまでにない価値の創造により、顧客の行動が変わることである。
●イノベーションを引き起こす源泉は、次の3つである。
・社会構造 ・心理変化 ・技術革新
これらを「イノベーションのドライバー(トライアングルドライバー)」と呼ぶ
●イノベーションは、①トライアングルでドライバーを捉える、②ドライバーをてこに新しい価値を創造する、③顧客の態度が変容する、④顧客の行動が変容する、という4ステップで起こる。この創出プロセスを「イノベーションストリーム」と呼ぶ。
●行動変容を起こす者と、価値創造を実現する者が、同じとは限らない。新しい価値を創造しても、顧客の行動をどう変えるのかという広い視野がないと、イノベーターにはなれない。逆に言うと、新しい価値を創造できなくても、顧客の行動変容と実現したいことを明確にすれば、イノベーターになれる。
●イノベーションの達成後、その行動変容をベースに新たなイノベーションを生み出すことができる。この「イノベーションの連続」で重要なのは、「行動変容」→ 新たな「ドライバー」を見立てる →「価値創造」とプロセスを進めていくことだ。
個人的には、イノベーション達成後に新しいイノベーションを生み出す「連続的イノベーション」は日本企業の伝統的な強みですので、意識すべき点だと思いました。


