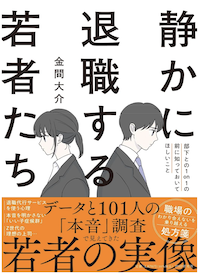Recommend Bookおすすめ書籍
静かに退職する若者たち
出版社/PHP研究所
<概要>
「1on1では笑顔だった若手が、なぜ突然辞めるのか?」 本音を隠す「いい子症候群」の実像を暴き、彼らの熱量(たぎり)を引き出す具体策を提示する一冊です。
<感想>
「即・短時間・多回数」という私のフィードバック論と方向性が完全に一致! 特に「私」を主語にして褒める視点は、若者の心理的ハードルを下げ、関係性を深めるための強力なヒントになります。
<印象に残ったフレーズ>
「周りと同じではいけない、個としての貴重な体験こそが君を唯一無二の存在にする」と教わり続け……それでもなお、他人と違う自分に自信が持てない。
<まとめ>
「壁打ち」を増やして業務への興味を引き出し、「組織貢献できている!」という実感を。 テンプレートな対話を、魂が震える「たぎる時間」へ変えていきましょう!
「1on1では笑顔だった若手が、なぜ突然辞めるのか?」 本音を隠す「いい子症候群」の実像を暴き、彼らの熱量(たぎり)を引き出す具体策を提示する一冊です。
<感想>
「即・短時間・多回数」という私のフィードバック論と方向性が完全に一致! 特に「私」を主語にして褒める視点は、若者の心理的ハードルを下げ、関係性を深めるための強力なヒントになります。
<印象に残ったフレーズ>
「周りと同じではいけない、個としての貴重な体験こそが君を唯一無二の存在にする」と教わり続け……それでもなお、他人と違う自分に自信が持てない。
<まとめ>
「壁打ち」を増やして業務への興味を引き出し、「組織貢献できている!」という実感を。 テンプレートな対話を、魂が震える「たぎる時間」へ変えていきましょう!
もっと見る